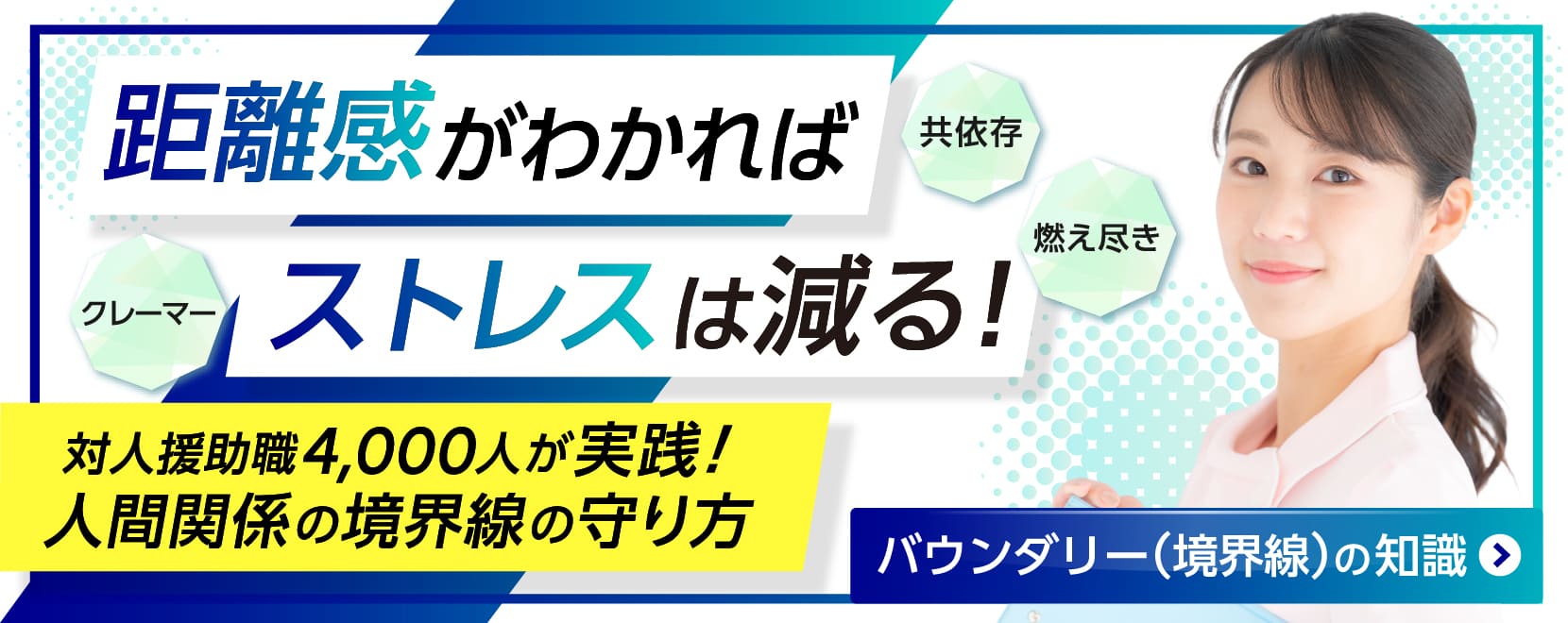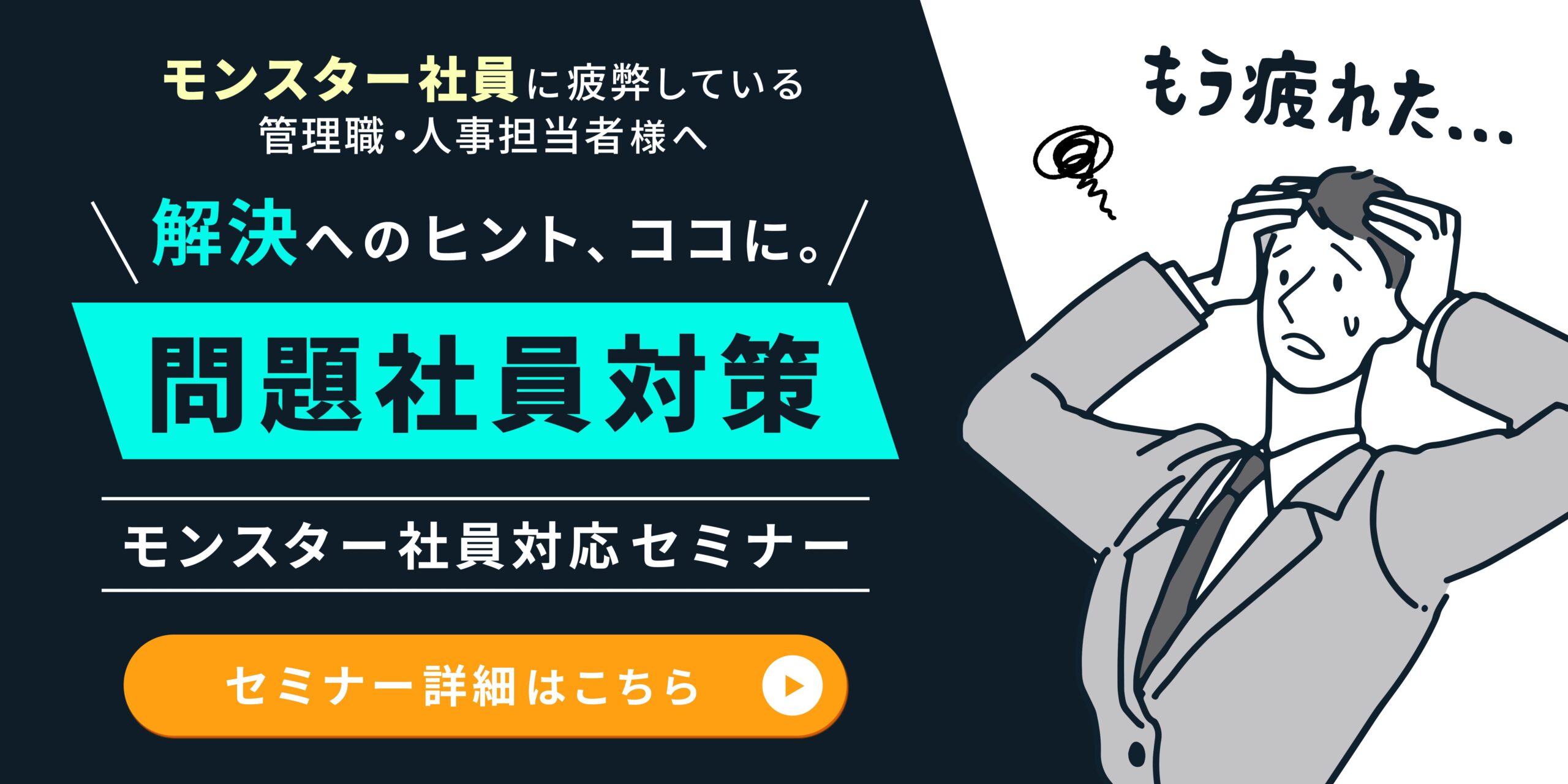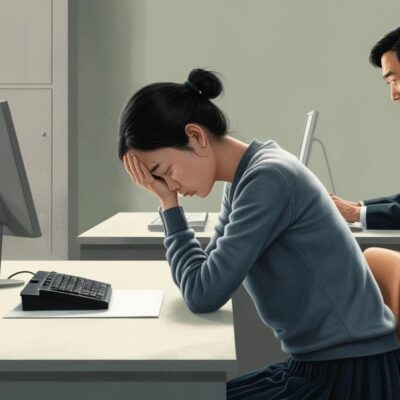普段、「反抗的な部下がいて対応に困る」といった相談を多く受けますが、中には「ずっと真面目で大人しかった部下が、急に反抗的になってしまった」というケースも見られます。

あれだけ真面目だったのに急に凶暴になるなんて、躁うつ病とか、メンタルヘルス問題ですかね?それとも、プライベートで何かトラブルでもあったんでしょうか…
このように、管理職としては戸惑い、その背景にある原因を「社員個人」に求めることが一般的かなと感じます。
ただ、私が詳しく職場の状況などを聞いていくと「人間関係の相互作用」で説明がつくケースがいくつもあります。
「人間関係の相互作用」と言われてもなんのことだかわかりませんよね。
言い方を変えると、「部下が問題を起こしている」というのは事実としてそうなのですが、より深く見ていくと「職場の問題により、部下が問題を起こしている」のです。
今回はその一例を紹介いたします。
まず、ちょっと違和感を覚えるかもしれませんが、「急に子どもが暴力的になった」という母親の相談と、「急に部下が反抗的になった」という管理職の相談を並べてみますので、両方読んでみてください。
※ブログ執筆者 AIDERS 代表 山﨑正徳のプロフィールは こちら
目次
「いい子だった娘が急に反抗するようになりました…」

中2の娘が急に暴力的になって、すごく反抗するので困っています。この3か月くらいおかしいんです。
言うことをきかないし、すぐに怒鳴るし、一昨日は壁を蹴って反発しました。見かねた夫が対応すると「お前は関係ねーだろ!仕事ばかりしてるくせに!」とか言って部屋にこもってしまって。担任の先生に相談したら、学校では全くそんなことないし、むしろ真面目らしくて。先生はとても驚いていました。
娘には高2の兄がいます。実はお兄ちゃんの方が中3から不登校で大変だったんですよ。高校に進んでも、学校に行けなくて。それで退学して、半年前に通信制の高校に入りなおしたんです。それから兄の方は落ち着きました。学校に行かなくてもよい環境が安心したみたいです。
この2年くらいは私はお兄ちゃんの方で大変で、娘はいい子だったんですよ。やっと兄の方が落ち着いたと思ったら、今度は娘です。まいりました…
「真面目だった部下が突然凶暴になってしまいました…」

先月から、一人の部下が突然わがままを言い出して、仕事を拒否するようになりました。
うちは課員が3人います。ベテランのAさん、いつも真面目なBさん、新人のCさんの3人です。
私が困っているのはBさんの行動です。会議中に突然「私はもうできません!いっぱいいっぱいなんで!」と感情的になって、仕事を拒否するのです。確かに仕事はけっこう任せていますけど、それはみんな同じですし、彼女は今までほとんど不満などいう人ではなかったんですよ。あまりにも感情的なので、空気を呼んだCさんが「僕がやりますよ」と言って仕事を一部引き取ってくれました。
実は、去年までベテランのAさんの体調が悪くて、うちの課は大変だったんです。Aさんがけっこうな曲者で、体調が悪いと言うものの精神科とかを受診してくれないし、それでいて「体調が悪いから在宅勤務にしてください」「出社しろというならしますが、もし私がコロナに感染して重症化したら責任取ってくれるんですか?私は体調が悪いんですよ」とかいって一方的に在宅勤務を続けてしまい、半年くらい会社に来てくれなかったんです。
新人のCさんの教育もしないといけない中、私とBさんで課を回していた状態です。Bさんは特に文句を言わず、真面目にやってくれてとても助かりました。
曲者のAさんについては、結局のところ人事が動いてくれて、「精神科を受診して診断書を出さない限り在宅は認めない」と言ってくれて。そこからAさんは出社しています。Aさんは何があったのか、人が変わったかのように真面目に働いてくれていて、新人のCさんの面倒もよく見てくれています。
ようやくひと段落したと思ったら、よりによって一番頼りになるBさんがこんな感じになるなんて。本当に困りました…。
誰かの犠牲によって成り立っている家族や組織もある。
この二つの事例は実際に私が受けた相談なのですが、二つとも同じ構造で成り立っています。
読んでいただいて、気づくことはありませんか?
初めの家族の娘も、会社のBさんも、もともとは「犠牲者」だった可能性があるのです。
母親は兄の不登校で疲労困憊で、娘は「真面目ないい子」でいないと母親は倒れてしまったのかもしれません。
Bさんも、いっぱいいっぱいの課長と新人のCさんに挟まれ、「文句ひとつ言わずに働く社員」でいる必要があったのかもしれません。
このように、人は集団の中でバランスをとります。そのために、時には自分が犠牲になることもあるのです。
娘もBさんも、本当はもっと愚痴を言いたかったのかもしれない。
兄や母親に、課長やAさんに文句を言いたかったのかもしれない。
でも、それもできずに溜め込んでいたのです。
お兄ちゃんの問題がようやく落ち着き、母親にも余裕が出てきた。Aさんが職場に戻り、課長も余裕が出てきた。
そこで、これまでの不満が一気に爆発することもあるのです。
「わかってもらえなかった」
「気づいてもらえなかった」
「なんで私ばかり我慢させられるのか」
今度は自分の番だとばかりに、問題が起きていきます。
このようなケースでは、ただただ「部下が反抗的になった」と個人の問題にしていては解決しません。
問題の構造に気づき、職場が「私たちの問題でもあるんだな」とまずは認めて向き合うことが必要なのです。
※「真面目な部下が急に反抗的になった」という問題について、当然ではありますが、今回紹介した事象にすべてが当てはまるというわけではありませんので、ご確認ください。
「人に関心を持つ」とは、どういうことか。

Bさんがまさかそんなに一人で抱え込んでいたとは思いませんでした。当時、私からは「大丈夫?」と声をかけたんですけど、「大丈夫です」と言っていました。
「体調が悪かったりしたらいつでも言ってほしい」とも伝えていましたけど、特に何も言ってこなかったんです。もちろん、Aさんに対する不満なんて聞いたことありませんでした。
だから、大丈夫なんだな、前向きに仕事に取り組んでくれているんだなと思っていました。そんなに大変なら言ってくれたら良かったのに…。私はどうしたら良かったんでしょうか。
最後に、「人に関心を持つ」とはどういうことなのか、私の考えを解説します。
職場でメンタルヘルスケアを推進していくためにも、「日常的に部下の様子に関心を持つ」ということは大前提となります。
ただ、この「関心を持つ」という言葉は抽象的な表現なので、ただただ「部下に関心を持ちましょう」と言われても、人によってかなり温度差が出るものです。
「残業が増えたけど大丈夫?」と声をかけたら、部下が「大丈夫です」と答えたので、「何かあったらいつでも相談してね」と伝えて話を終えた。
上司からしたら、残業が増えた部下に声をかけたので、「十分に関心を示した」ととるかもしれませんが、人に関心を持つというのは実はこれだけでは不十分です。
部下が「大丈夫です」と言っても、さらに一歩踏み込んで気持ちを想像する。
私の考える「人の気持ちに関心をもつ」ということは、自分と相手の関係も含めて、相手の気持ちを想像するということです。
「大丈夫?」と聞かれた場合、本当は大丈夫ではなくても「大丈夫です」と答えてしまう関係はありますよね。上司と部下がその典型だと思います。
部下は上司の評価や印象を気にしますから、本当に大変でも「大丈夫です」と言ってしまうことは珍しくありません。
だから、相手が「大丈夫です」と言ったとしても、さらに一歩踏み込んで、相手の気持ちを想像することが「人に関心を持つ」ということなのです。

私がいつも忙しそうにしているから、私に気を遣っているのかも。『大丈夫』と言わせてしまっているのは私の方に原因があるのかもしれないな…。

彼はまじめだし抱えやすいところがあるから、本当はけっこう無理をしているのかもな…。
相手の人間性をきちんと把握しておけば、自分が「大丈夫?」と聞いたときに相手ならどう答えそうなのか、そしてそれは本心なのか、などを想像することができますよね。
だから、「大丈夫?」と声をかけることが「関心を持つ」ことなのではなく、相手の回答の背景にある心理を、自分との関係性まで含めて想像することが、「関心を持つ」ということなのです。
「自分の気持ちに関心がない人」は、人の気持ちに関心を向けられない。
ここまでの話を聞いて、すんなり理解できる人もいれば、私がとても難しいことを話していると感じる方もいるはずです。
なぜなら、「人に関心を持つ」ためには「自分自身に関心を持つ」ことが大前提であるからです。
自分に関心を持つというのは、すなわち、自分の気持ちをわかろうとすることです。
辛さを感じた時に、自分はどれだけ辛さを感じているのか、そして何に辛さを感じているのか、どうなれば良いと思っているのかなど、内省する習慣を持っている人は、部下が「辛い」と言った時もより想像を巡らせることができます。

どれだけ辛いのかな?どんなことにストレスを感じているのかな?なにか自分に言いづらいことはないかな…
このように、相手の気持ちをより深く理解しようという意識が自然に働くのです。
逆に、自分の気持ちに関心を持つ習慣がなければ、自分が「辛い」と感じていても「辛いなんて考えるだけ無駄」「この仕事は自分がやるしかないんだから、黙って終わらせるだけ」などと考えてそれで済ませてしまいます。
だから、目の前で「辛い」と言っている部下がいても、そこから想像を巡らせて相手の気持ちを想像することができないのです。
つまり、管理職自身がよく内省し、自分の気持ちと向き合う習慣を持つこと。そして、メンタルヘルスを良好に保つ意識を持つこと。
職場でメンタルヘルスケアを推進していくために、まずはその意識を強く持ってください。
ここまで読んで、「まさに自分のことを言われているな」と感じた方は、「自分の気持ちに関心を持つ」ことを実践する初めの一歩として、以下のブログ記事をぜひ読んでみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

最新記事 by AIDERS 代表 山﨑正徳 (全て見る)
- ディベート・ハラスメントの正体 | 突然始まる、言葉と感情の暴走。 - 2026年2月11日
- 「傍観ハラスメント」はなぜ起きるのか。ハラスメントが蔓延する機能不全組織の特徴を徹底解説。 - 2025年4月25日
- 注意するとすぐに「パワハラですよ」と言うハラハラ社員への職場の対応方法 - 2024年12月17日